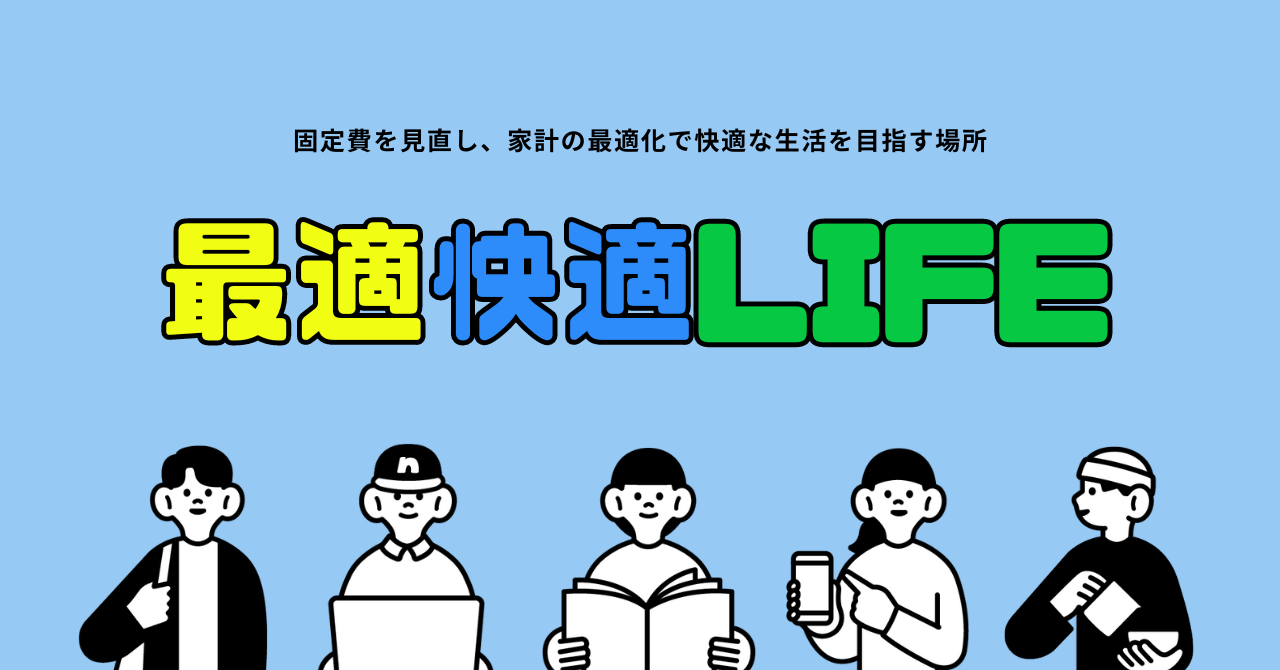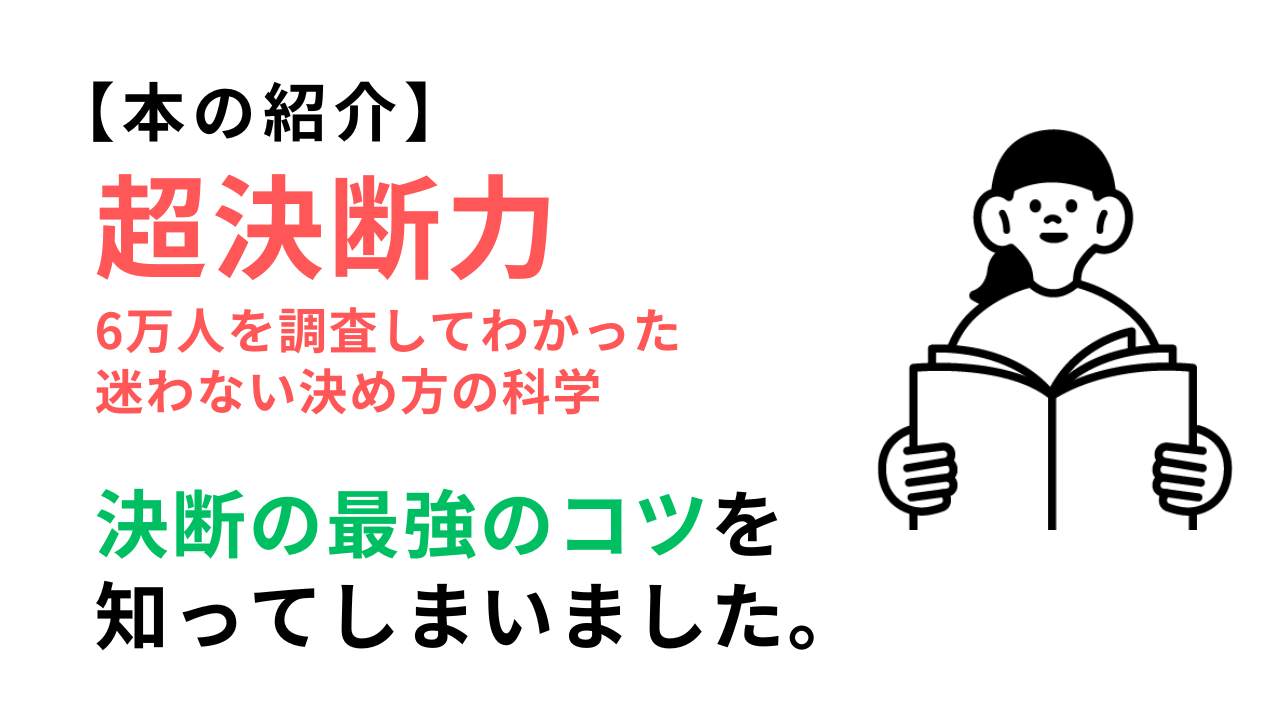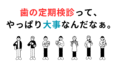Audibleで「超決断力ー6万人を調査してわかった 迷わない決め方の科学/メンタリストDaiGo著」を聴きました。
この一冊もまた、DaiGoさんの知識量とその知識を自分の中にしっかり落とし込んで人生を豊かにしていっているんだということがよく分かる一冊でした。
決断力とは、いかに早くミスなく何かを決めることで、それには自分の中にシステマチックに決断できる決断のルールを確立することが重要だという話から始まりました。
1日で決断する回数は最大で3万5千回。とんでもない回数ですね。
決断をするという回数と時間が多ければ多いほど、優れている人もミスをするので、なるべく考える回数を減らすことで脳への負担を減らし、ミスを少なくできるということでした。
そして、システマチックに意思決定できると決断のスピードも早くなるのです。
そのための方法として「クネビンフレームワーク」という手法が効果的だということでした。
これは自分の取り巻く状況がどういうものかを観察して、それに合わせた決断方法を選ぶために考え出されたもので、次のように分類されます。
| 状態 | 状況 | 例 | |
| ① | 単純/Simple | やるべきことがわかっているけど決断できない | ダイエット |
| ② | 面倒/Complicated | どの選択肢が一番いいかを決断できない | 引っ越し、転職 |
| ③ | 複雑/Complex | 予測できないことだから決断できない | 投資、結婚 |
| ④ | 混沌/Chaotic | 答えがないから決断できない | ずっとこの人生でいいのか |
この分類をもとに、その場その場で最善の決断が下せるよう導く仕組みです。
自分がどのような状況に置かれているのかを把握せず、やみくもに決断しようとするとそれだけ脳が疲れて、決断が遅くなったり、ミスしてしまったりします。
クネビンフレームワークを使うことで、決断をより早く、確実にして脳の負担を減らすことができるということでした。
①の単純はやるだけ、やらないだけです。やらないといけないとわかっているのにやらないのはただの怠慢です。やるためのノウハウは習慣化などを活用していきます。
②は日常で最も多いケースで、不確定要素もあるので決め手に欠けたり、試してみないとわからないというものばかりです。専門家に相談して知識を借りるのがいいということでした。
③は理想的な解は何となく見えているものの、どうすればその解にたどり着けるかわからず、前提となる状況も変化するものなので、適切な解がわからない場合も多いです。この時には失敗しても良いパターンを何個かトライして、解決できそうな状況が出てくるのを待つのがいいということでした。
④は原因と結果の因果関係もよくわからず最適な答えのない状況のことで、この状況では私達自信がコントロールできる問題がほとんどないので、複雑な状況が複雑に絡み合い、解決が厳しい状況です。何かに取り組んでも、すぐには答えが出ないことが多いそうです。解決のためには、解決のパターンを探すよりもダメージを最小限にして、何が安定し、何が安定していないのかを把握し、④の「混沌な状況」を③の「複雑な状況」に移行させた上で何らかのいいアイデアが浮かぶのを待つのがいいということでした。
これらが決断の状況なので、まず自分の置かれている状況を把握し、その後に④→③→②→①と移行させていくことで決断の難易度を避けていくことが決断の秘訣だそうです。
もしなかなか移行できない時には、「今絶対に必要なものは何か?」という問いを自分にしてみると、状況が移行しやすくなるとのことでした。
本の中ではDaiGoさんの実際の選択や、①〜④の具体的なノウハウ等もかかれていますので、興味のある人はぜひ読んでみてください。めっちゃ勉強になります。
私はこのクネビンフレームワークを知っただけで気持ちが楽になった気がします。
次は本の中で紹介されている最強の決断のルールをまとめたものです。
| 状況 | 最強の決断ルール | |
| ① | 単純/Simple | VARIの活用 V…Values(価値)自分の価値観をリストアップする A…Automation(自動化)自動化できるか考える R…Rational Decision Making(理性的な決断)決断可能な選択肢をリスト化する I…Intuition(直感) 感情に沿って考えてみる |
| ② | 面倒/Complicated | 「はじめの一手」を持っておく(デフォルト設定) |
| ③ | 複雑/Complex | ・デフォルト設定をいくつか試し、感触のいいものを続けて、 別の選択肢を試しながら成功へと近づく |
具体的な内容は実際に本を聴いて(読んで)みた方が理解が深まるので、ぜひ聴いて(読んで)みてください。
決断に至るまでのプロセスにも様々な知識やスキルが関係していて、今まで何気なくしていたこともこの内容を知っていればもっと早くもっと確実にもっと効率よくできるのだということに気づきました。
やはり学びは大切。これからもしっかり学んでいこうと思います。